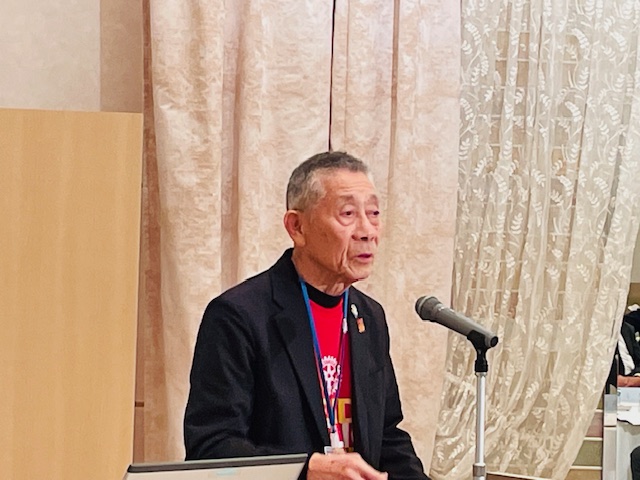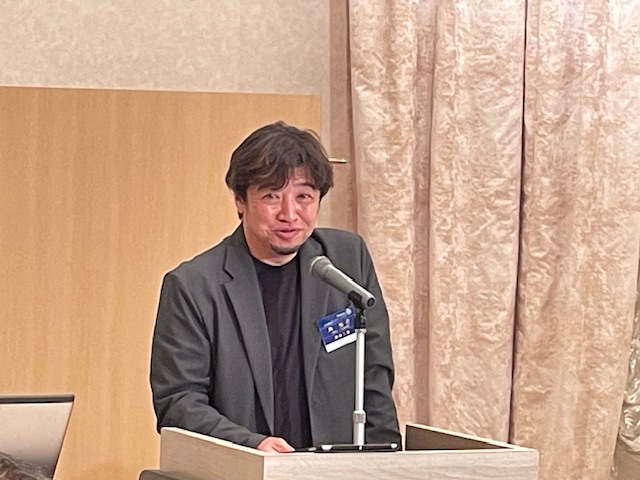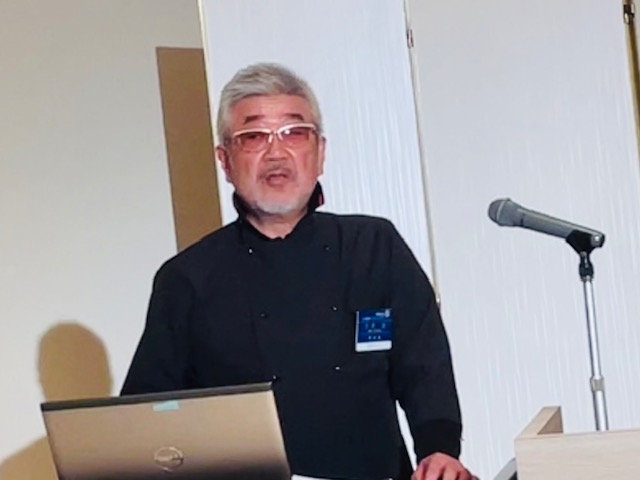会長の時間
今週の会長の時間は、アスファルトについてです。
アスファルトは大きく分けると「石油アスファルト」と「天然アスファルト」に分けることができます。
石油アスファルトの製造工程
輸入されてきた原油はまず常圧蒸留装置に導入され、ガソリン・灯油・軽油・ナフサ・LPGが
取り出されます。これらを取り出した残りを常圧残油と言いますが、常圧残油はさらに減圧蒸留
装置に送られて、真空蒸留という方法で減圧軽油が取り出されます。この減圧軽油を取り出した
残りが減圧残油と言われるもので、この一部がアスファルトになります。
一方、天然アスファルトは、原油が地表近くで風雨に晒されて酸化し、揮発成分を失って
重質部分が残ったもので、幕末から明治にかけて多く使われていたそうです。
しかし、天然アスファルトは固い石のようなもので、液状のアスファルトにするには、多くの手間や
コストがかかってしまうため、現在ではほぼ使われていません。
ここで、日本初のアスファルト道路を紹介しますと、1863年(文久3年)に建設された長崎県の
「グラバー邸」と、1878年(明治11年)に建設された東京都秋葉原の「昌平橋」です。
なぜ2つの「日本初」があるのか、これはアスファルトの原料が関係していて、「昌平橋」は
秋田県で採掘された天然アスファルトが使用されているのですが、グラバー邸では石炭から
発生するコールタールが使用されているそうです。アスファルトとコールタールは厳密には
成分が異なることから、日本アスファルト協会のサイトでは、日本初のアスファルト舗装は
「昌平橋」と紹介しています。しかし、架け替え工事が行われたため、今では昌平橋は見ることが
できません。
ちなみに、東京の信濃町駅近くの明治神宮外苑聖徳記念絵画館前に1926年(昭和元年)に
建設された現存する日本最古級のアスファルト舗装が残っています。
一般的にアスファルト舗装の寿命は10年から15年と言われているので、グラバー邸も含めて
貴重な構築物なので、旅行などで訪れた際は気にかけてみてください。歴史が好きな方は
グラバー邸に行って、坂本龍馬や維新志士が踏みしめたと思いながら歩くと、楽しみが1つ
増えるかもしれないですね。
以上、今週の会長の時間でした。